ウッドボンゴを修理してみた
タイトボンドを購入しました。namimoriです。
色々と作ってみたいもの・修理したいものがありますが、まずはこのウッドボンゴ(ボンゴカホン)を修理してみました。
修理部分
まず、エンブラ(口径の大きい方)のシェル(胴)部分がパックリと割れてしまっています。
また、木製のヘッド(打面)がシェル部分から一部剥がれてしまっています。(写真ではわかりにくいですが、シェルの割れ目上から両側数センチにわたって剥がれています。)
叩いた際にこれら隙間が開いたりぶつかり合うことで、パキッとした不快な高音ノイズが打音に混ざってしまう状態です。
作業手順
接着にはタイトボンドを使用
接着にはタイトボンド(Titebond ORIGINAL)という木工用強力ボンドを使いました。ネット情報になってしまいますが、木製楽器リペアの現場でよく使われる接着剤のようです。[1][2]
(硬化後の木部との音響インピーダンス整合の問題もあるでしょうから、最適な音質を得るために本来は使用木材に応じて接着剤を選定する必要があると思われます。しかし、手早く安価にとりあえず使える状態にしたいという今回のような場合には汎用的なもので良いという判断で使ってみます。)
参考リンク
接着剤を流し込みクランプで固定
時短のため本当は2カ所同時に接着したかったのですが、クランプが1つしかなかったので片方ずつ行いました。ボンドを流し込みなるべく歪みが生じず力が加わるようクランプで固定しました。圧力を加えると接着部から余剰のボンドが流れ出すので乾く前に拭き取っておきます。シェル部分の接着の際にはクランプの他に輪ゴム(平ゴム)をかけて元の円形に力が加わるよう調整しました。(おまじない程度かもしれませんが。)
ヘッドの接着の際は剥がれの中心部分に力が加わるようクランプ固定しましたが、クランプを複数使ったり板材を使うなどして、なるべく接着部分全体に圧力が加わるようにするべきだったと作業を終えてから思ったりもしています。
固定状態でそれぞれ24時間ほど静置しました。
接着はとりあえず成功・若干のズレはあるかも
シェル・ヘッドの接着はどちらもうまくいき、打音の中に以前のような不快なノイズはなくなりました。
シェルを内側から見ると割れ部分がピッタリ閉じているように見えます。(画像内ナット・ワッシャーのすぐ右側が割れ部分。)
ただ、外側は割れの線が見えてしまっています。はみ出したボンドというよりは割れが閉じきっていない状態のように見えます。(ボンド自体はよく充填されており隙間はなさそうです。)
また、ヘッドも外側から見ると接着部分同士が閉じきっていない・ボンドが充填しきっていないように見えます。
以下のような接着剤の注入器を使い、多めにボンドを充填すべきでした。
叩いてみると音自体には問題ありませんが、もしも接着部分同士がしっかり合わさっていないとなると強度に不安が残ります。
道具と技術次第。確実さを求めるなら専門家へ。
やはり素人の自分には道具も技術も足りないと感じました。当たり前のことですが、確実さや仕上がりの綺麗さを求めるのであればお金を払ってプロにお願いするのがベストだと改めて思いました。
今回は安価に手早くとりあえず使えれば良い、壊れたらまた同様に接着すれば良いという、そしてなにより自分でやってみたい、という場合のDIY修理の紹介記事として見てもらえればと思います。











3.png)

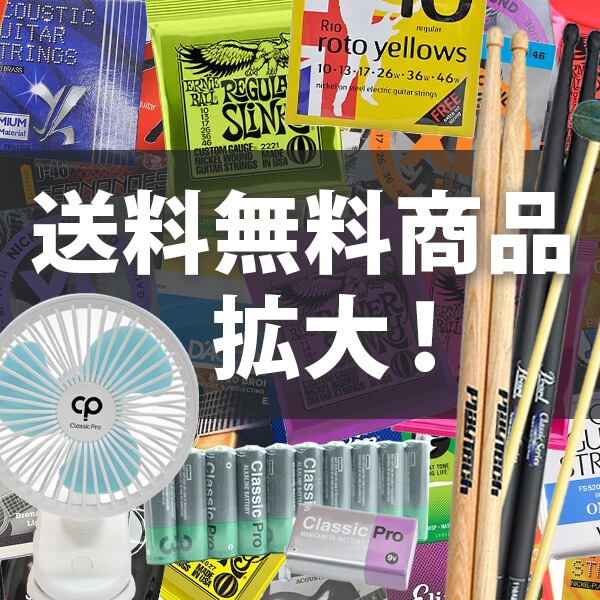



clone_withGT-1.jpg)


