VOX MINI3とGT-1でのミニライブ事例
先日、友人の結婚披露宴に出席し余興でちょっとしたバンド演奏をしてきました。音楽ライブ会場ではないので音響設備に制限がありましたが、手持ちのVOX MINI 3が役に立ったので紹介します。
VOX MINI 3 の特徴
VOX MINI 3(以下、MINI3)はアンプモデリングとエフェクター内蔵の3Wポータブルギターアンプです。アンプモデルはクリーン系からハイゲイン系まで充実しており、エフェクターもコンプやコーラスなどの定番エフェクトとディレイ/リバーブとの2系統を一種ずつ同時にかけられます。また、モデリングを通さないクリーン・フラットなLINEモードもあるので、エレアコやキーボード用のアンプとしても使えます。さらに、ギターチャンネルと共通のディレイ/リバーブが独立して使えるマイク入力もあり電池駆動も可能なため、これ一台で野外での弾き語り用ポータブルミキサーPAとしても使えます。
古い機種のため現在はマイナーチェンジ版のVOX MINI3 G2とともに廃番で、現行品ではVOX MINI GO 3が(おそらく)後継機となっています。
実施した活用例
バンド編成
編成はアコースティックバンドで、
- ボーカル→マイク(会場PA)
- コーラス→マイク(会場PA)
- カホン→マイク(会場PA)
- ピアノ(キーボード)→DI(会場PA)
- エレキギター→VOX MINI3(持ち込みアンプ)
- アコースティックギター→VOX MINI3(持ち込みアンプ)
の6パートでした。会場の広さや常設機材の入力数の関係上、ギター以外の4つは会場PAからの音出しで、エレキとアコギは持ち込みのMINI3でまかないました。
会場はテーブル~10卓・着席~60人程度収容の披露宴会場で、アコギやカホンは生音のみの音量では厳しい広さでしたが、
- キーボードとボーカルが会場PAからメインで聞こえれば良い
- ギターは2本ともサブ・装飾的に聞こえれば良く音量控えめでもOK
- 披露宴の余興演奏なのでライブ会場ほどの大音量ではない
という条件下で、3Wの小型アンプでも十分な音量で鳴らせました(ボリュームも上に余裕が残る範囲・電源アダプタ駆動)。演奏の動画もあとで見せてもらいましたが、エレキ・アコギともにサブ伴奏的な役割の音量でありつつしっかり抜けてくる音で他のパートとのバランスが取れていたと思います。
ギターとアンプの接続
エレキギターの音作りは全てマルチエフェクターGT-1で行い、MINI3のモデリングは使わずGT-1の出力音をそのまま鳴らすLINEモードで使いました。MINI3のLINEモードではLOWとHIGHの2バンドEQが使える[1]ので、会場の音の回り方や他パートのミックスとの兼ね合いでマスターEQ的に使いました。エレキ側MINI3のエフェクト(リバーブ)は不要でしたが、MIC IN(アコギ)側にかけるためにRoom・最小に設定しました(アコギ側はSENDノブでリバーブ量を調整できます)。なお、今回はシンプルな音作りで音色の切り替えも手元のコントロールのみで十分だったので、荷物を減らすためにGT-1は使わずMINI3のアンプモデリングとエフェクトのみで音作りしても良かった気がします。
アコギはパッシブのマグネットピックアップ (FISHMAN NEO-D Humbucking) をそのままMIC IN(マイクチャンネル・アンバランス)に接続しました。本来、これはインピーダンスや信号レベルが合わない仕様外の使い方です。特にインピーダンスがハイ出しロー受け状態となりピックアップ本来の音質は発揮できません[2]。ただ、演奏全体としてはピアノ・カホン・ボーカルがメインで聞こえれば良く、アコギの場合は生音もあるので、サブ的に音量が稼げればOKということで今回の使い方になりました。まあ、普通にやめた方が良いです(愚直にやるならDI等でインピーダンスやレベルを合わせます)。ちなみに、上述のとおりギターch.とは独立してディレイ/リバーブをMIC ch.にかけられる(種類はギターch.と共通)ので、少し強めにかけて全体に馴染ませました。なお、ディレイ/リバーブノブの設定値(量)はMIC IN 側には適用されません。MIC IN側のエフェクト量は完全にSENDノブの設定値のみで決まります。
終えてから気づきましたが、どうせエレキ側もMINI3のアンプモデリングは使わずLINEモードなので、手持ちの2chミキサープリアンプ(Birdland acoustic mixer)でエレキとアコギの音をミックスしてギターチャンネルに入れれば良かったと今更ながら思っています。リバーブ量は共通となりますが、この方法なら無理にマイクインプットを使う必要もありません。
まとめ:手軽に持ち込め機能も充実
出力は3Wしかない小型アンプですが、小さな会場や今回のようなアコースティックユニット系では十分な音量が出ます。ギター/ラインとマイクの2系統入力があり、リバーブ/ディレイもミキサーのセンドエフェクト的に各chに独立した量をかけられるので、ポータブルミキサーとしても便利に使えます。また、GT-1とともに今回のシステムは全て電池駆動でOKなので、野外パフォーマンス用途の他、今回のようにセッティングやリハに時間が取れなかったり会場設備(特に電源の位置など)が音楽ライブ向けでない状況にも柔軟に対応でき大変有効です。
ちなみに、MINI3は電池駆動の場合単三乾電池6本の9V駆動なので少し改造すれば以前購入したPower Cable USB/DC9V と組み合わせてモバイルバッテリー駆動できるのでは?と目論んでいます。電池交換や買い換えの手間・コストを避けられる他、消費電流や電源ノイズの問題はありそうですがエフェクターと共通の電源で使えるとさらに便利になりそうです。(ちなみに現行品のVOX MINI GO 3 は5V・USB Type-C入力でのモバイルバッテリー駆動が可能です。)




3.png)

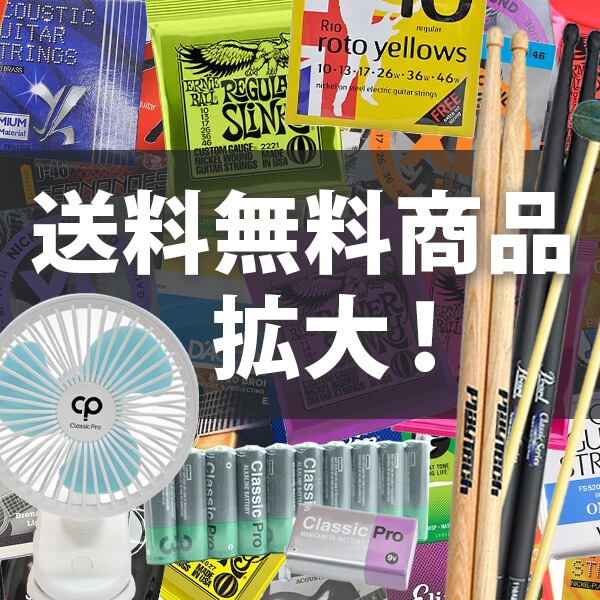



clone_withGT-1.jpg)


